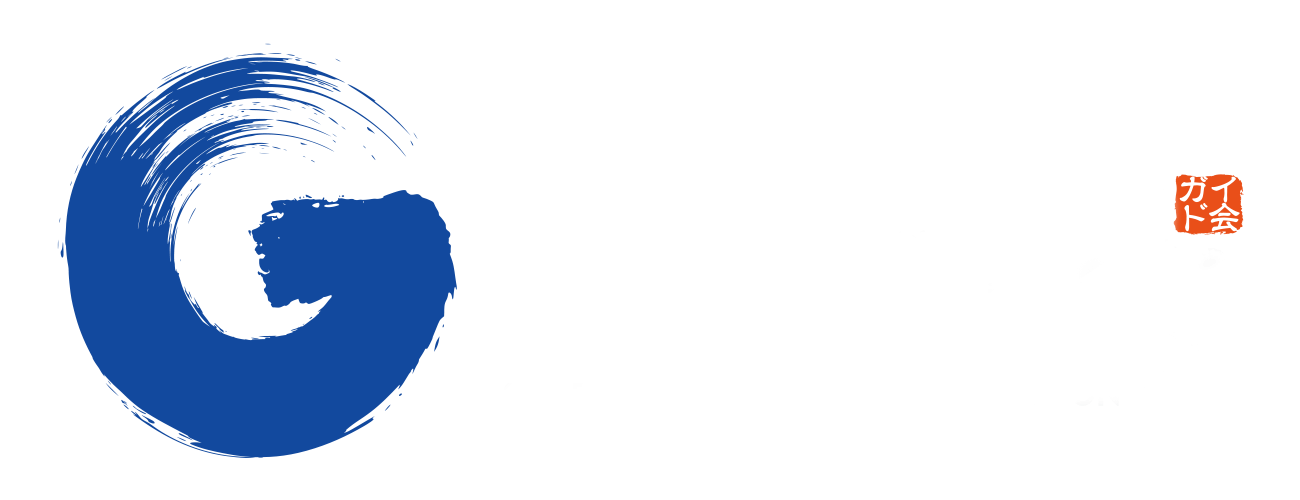7日は三保真崎から鉄が海の情報をお届けしています
MDFに伴って、ガイド会のイベントが目白押しでしたが予定が合わず、またサプライズの登場も熟慮しましたが、体調が思わしくなかったため断念しました
先月は、中旬に西オーストラリアに1週間ほど研究出張していたため、海の様子は前半と後半に二分して把握する状態でした
その変化があまりにも劇的で、帰ってから潜って笑ってしまいました
前半は

シオミドロがモヘアのセーターでも敷き詰めたように繁茂して、大半の生物がその上に乗った状態で観察されたので、リサーチが楽チンでした


シロガヤも元気で、ワレカラやウミウシが沢山観察できました



戻ってから潜ると、あれほど繁茂していたシオミドロが全く消し飛んでいて、これはこれで生物を探しやすい状態に変化していました

フサカサゴ系の幼魚も観察できました

SNSにも投稿しましたが、これまで見たことがないようなサイズのラッパウニを見つけました
比較のために置いたミノーの大きさが約15cmほどなので、サイズが分かると思います
その後、気になってラッパウニが局所的に繁殖しているエリアに行ってみたのですが、5〜6cmほどの個体は見つかるのですが、2cmを下回る幼体を観察することはありませんでした

放卵放精によって拡散するわけですから、数が多い場所に必ずしも幼体が多く居るわけではないですね
このカットに中だけでも9個体のラパウニが確認できます
こんな場所が何十ヶ所もあります
このエリアだけでも2〜300個体は生息しているのではないでしょうか
ラッパウニだけでなく、最近はシラヒゲウニも増えています
なんなら、アカオニガゼも増えてきています
ダイバーの知識量が蓄積されて、それが多くの優れた観察眼となって環境を俯瞰視した時に、これまでとは違う景色を見ています
その景色や生き物の変化をどのように評価して、次の世代に伝えてゆくかという使命があるような気がします
人によって伝え方は様々だと思いますが、良い悪いではなく、事実を正確に、湾曲せずに伝達することが大事だと思います